bioRxivでプレプリントを公開していた、GFPのゲル内リフォールディングの論文がAnalytical Biochemistry誌に掲載されました。生化学的な実験手法に重きを置いた、昔からあるジャーナルです。派手さはありませんが、私の持っている論文を確認すると結構読んでおり、実験手法の開発という内容も、このジャーナルにフィットしていたかと思います。オープンアクセスですので、購読しているかに関わらず、誰でも読めます。
Shiratori, M.; Tsuyuki, R.; Asanuma, M.; Kawabata, S.; Yoshioka, H.; Ohgane, K. In-Gel Refolding Allows Fluorescence Detection of Fully Denatured GFPs after SDS-PAGE. Anal. Biochem. 2025, 702, 115861. https://doi.org/10.1016/j.ab.2025.115861.
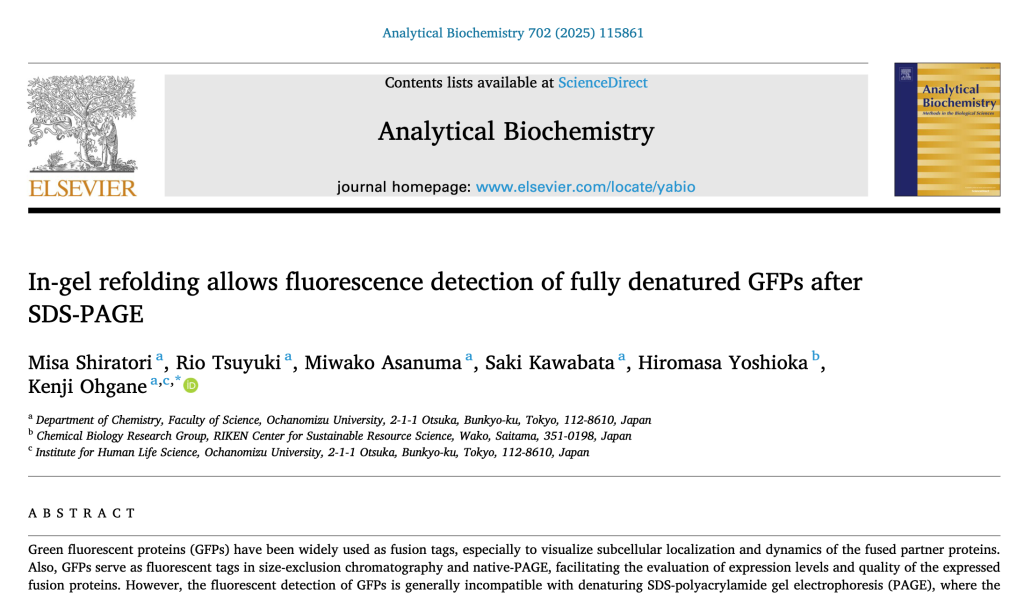
プレプリントとして査読前の原稿はbioRxivで公開済みですが、査読を経てほぼ全ての図 (Figure 1-5)が新たな図に置き換わり、質も高くなっているかと思いますので、プレプリントではなく今後は査読済みのこちらをご覧ください。
このような国際雑誌への論文の投稿では、まずエディターが内容を確認し、専門家数人に査読を依頼し、査読者が評価を行い、問題点や修正すべき点を指摘します。それらの指摘事項を、執筆者側で再実験やデータの追加で対応し、十分に要求を満たせばアクセプトされ、掲載という流れです。
今回、投稿からアクセプト・掲載まで、ほぼ6ヶ月がかかりました。最初の三ヶ月は理由はわかりませんがジャーナルの事務局・エディターのところで原稿が止まっていたため(しばしば起こります)、実質的には三ヶ月(だったはず)ということになります。査読者二人の対応は非常に早く、原稿が回って1週間で査読結果が届きました。査読は二人ともおおむね好意的ではありましたが、”定量的な評価”、”再現性を統計的に示すこと”が要求されました。その他、適用可能なGFPの種類などの点で”too preliminary”ではないかというコメントもありましたが、これまでに知られているGFPの変種全種類でリフォールディング可能かを調べるのは簡単ではなく、どのGFPで試すかも明確な基準がないことから、今回の論文の範囲外であろうと考えています。定量的な解析と統計解析については、論文に載せていたほぼ全ての図で(私たちなりに)かなりしっかりと行い(2ヶ月半)、図や本文をリバイズ(改訂)し、アクセプトに至りました。
B4白鳥さんには卒研発表直後から3月にかけてかなりの数の実験 (SDS-PAGEゲル作成、電気泳動、リフォールディング)を行ってもらいましたが、無事アクセプトになり報われたかな、と思います。
大金